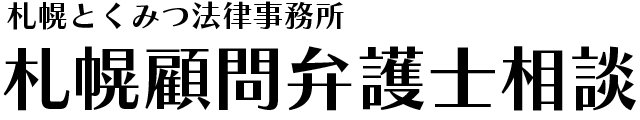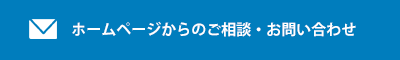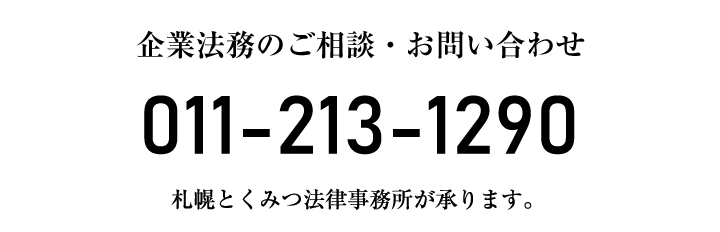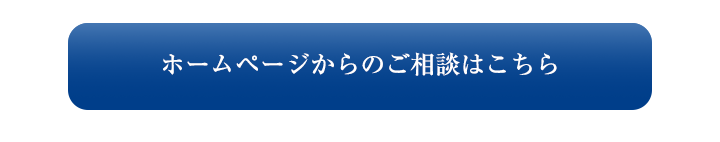企業法務コラム

建設業者が直面する危険のあるトラブルや法律問題
施工に関するトラブル
建設業は主に建築事業と土木事業に区別されますが、建設業法で定められる建設工事には電気工事、板金工事、塗装工事、防水工事、造園工事など、様々な種類のものがあります。
建設業において発生する恐れのあるトラブルは、まず施工に関するものが考えられます。
施主から施工内容に不備があることなどを主張されて、工事の中止を要求されることや、工事代金の支払いを拒否されることがあります。
また、その際、施主がこちらに無断で他社へ工事を依頼するなど、問題が複雑化することもあります。
工事内容の追加や変更に伴う費用負担をどうするかという点も、トラブルになることが多い問題といえるでしょう。
さらには、昨今ではカスタマーハラスメント防止のための体制整備が企業に求められていますが、施主などがカスタマーハラスメントといえるような行動に出たときに、従業員を守るためにも企業は適切な対応を取ることが必要となります。
元請や下請との間のトラブル
建設業を営む企業として、元請や下請の業者との取引や関わりは避けて通れないものと思われます。
このような繋がりは、自社の経営を安定させるなどのメリットを企業に与えますが、他方で、トラブルの要因となることもあります。
例えば、施主と元請との間で生じたトラブルを理由に、元請から自社に対する代金の支払いが遅延するなどの場合です。
この場合、民法や建設業法などを踏まえた適切な対応を検討する必要があります。
また、このように業者間の取引が継続的に行われている場合、他社や自社が倒産する際には互いに大きな影響を与えることになります。
したがって、取引先や自社に倒産の恐れがある場合は、仕掛かり中の工事の有無や、支払い未了の下請代金の有無などを踏まえた対応をする必要があります。
従業員との間のトラブルや労災問題
建設業者が法的紛争を抱える可能性のある問題は、顧客や取引先などの外部との関係だけではありません。
従業員との間で労使間紛争が生じる可能性も考えなければなりません。
賃金に関するトラブルや、退職や解雇に関する問題、さらにはハラスメントに関する紛争など、企業は労務管理において様々な配慮をしなければなりません。
建設業界において特有の問題としては、工事現場における労働災害があります。
企業は労働安全衛生法に基づく労働者に対する安全衛生対策をする必要があり、また、労働契約法に基づいても企業は労働者に対する安全配慮義務を負うため、これに違反して労働者に損害を生じさせた場合には損害賠償義務を負うこととなります。
労災保険では慰謝料が支払われないなど、全てが補填されるわけではないため、この補填されない部分について企業が賠償義務を負うかどうかが問題になることがあります。
また、労働安全衛生法違反に対しては企業に刑事罰が科される恐れのある他、行政処分がなされ、これらが公表される恐れもあります。