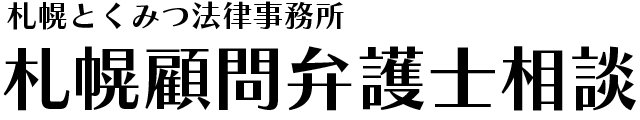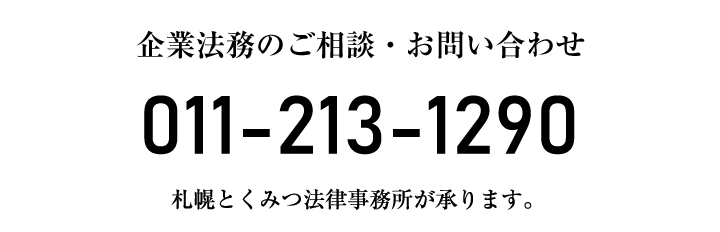企業法務コラム

製造業において想定される法的リスクやトラブル
製品の欠陥などによるトラブル
製造業者特有の法的リスクの代表的なものとして、製造物の欠陥によるトラブルが考えられます。
製造物の欠陥に関する損害賠償責任を定めた法律として、製造物責任法(P L法)があります。
損害賠償責任については民法にも規定がありますが、製造物責任について特に定めた法律として製造物責任法(P L法)があります。
一般的に、他者に対して損害賠償請求をする場合には、相手方に過失(又は故意)があることを立証しなければなりませんが、製造物責任については、製造物責任法(P L法)により過失の立証が不要とされています。
したがって、製造物に欠陥があれば製造業者は責任を問われる可能性が高くなり、製造業者はこのようなリスクに十分に備えなくてはなりません。
損害賠償のリスクに備え、PL保険への加入を検討することも一つの対策と思われます。
また、製造過程でのミスだけでなく、従業員による意図的なコンプライアンス違反により製造物の欠陥が生じることもあるため、このようなコンプライアンス違反を早期に発見するために、従業員が利用することのできる内部通報窓口を設けることも考えられます。
内部通報窓口の実効性を高めるために、外部の弁護士などへ窓口運営を委託する方法も効果的と言えるでしょう。
製品の欠陥によるトラブルの他、製品の商標権や意匠権、特許権などの知的財産権についても配慮する必要があります。
自社の製品の知的財産権を確保することは当然ながら重要ですが、他社の製品の知的財産権を侵害しないかどうかにも注意する必要があります。
取引先とのトラブル
製造業者は製造の過程において様々な取引先と連携しています。
もっとも、従来の慣行もあり、各取引先との契約書を取り交わしておらず、注文書や請求書のやりとりのみで済ませているということが多く見られます。
しかしながら、仕入品の不具合などのトラブルが生じた場合、契約書が無ければ思わぬ大きな紛争に発展する恐れがあります。
したがって、契約書の作成が重要となりますが、取引内容自体のみならず、秘密保持や競業避止に関する契約書の取り交わしを検討すべき場合もあります。
例えば、取引先との間で企業秘密を一部共有することとなる場合も多いと思われますが、その場合も秘密保持契約の締結などの対策がされていなければ、企業秘密が漏洩してしまう事態が生じかねません。
また、他社からの下請で製造業務を行うことも考えられますが、元請業者の対応が不当なものである場合、下請法違反などが無いかどうかを確認する必要があります。
さらに、昨今では国際市場へ進出する中小企業も増加していると思われますが、他国における法規制の確認や国外企業との契約内容のチェックなど、国内におけるマーケット拡大よりも十分な予防法務が重要となります。
この場合、前述の製造物責任の内容も国内よりもさらにリスクの大きいものとなる恐れがあるため、この点の確認や対策も必要となります。
労災事故や労務管理のトラブル
他の業種と比較し、製造業は労災事故が多く発生する業種といえます。
普段から労働安全衛生法などで規定される体制を整えることが必要となりますが、体制を整えていたとしても労災事故が発生してしまうことがあります。
その場合、労働基準監督署への報告や、労災保険による労働者救済の対応が必要となりますが、労災保険では補償されない慰謝料などの損害について、会社が労働者から損害賠償請求を受けるリスクがあります。
損害賠償発生の根拠は、会社の労働者に対する安全配慮義務違反があったことが中心となるため、普段からこの点に注意する必要があります。
また、昨今では、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントにより労働者がメンタルヘルスの不調を訴え、これを放置したことにより、この点の会社の安全配慮義務違反が問われる事例も多く生じています。
さらに、外国人雇用に力を入れている製造業者も増えてきていると思われますが、その場合も労務管理に注意する必要がある他、外国人労働者特有の問題として在留資格への配慮(従事できる仕事内容の確認等)も必要となります。
建設業者が直面する危険のあるトラブルや法律問題
施工に関するトラブル
建設業は主に建築事業と土木事業に区別されますが、建設業法で定められる建設工事には電気工事、板金工事、塗装工事、防水工事、造園工事など、様々な種類のものがあります。
建設業において発生する恐れのあるトラブルは、まず施工に関するものが考えられます。
施主から施工内容に不備があることなどを主張されて、工事の中止を要求されることや、工事代金の支払いを拒否されることがあります。
また、その際、施主がこちらに無断で他社へ工事を依頼するなど、問題が複雑化することもあります。
工事内容の追加や変更に伴う費用負担をどうするかという点も、トラブルになることが多い問題といえるでしょう。
さらには、昨今ではカスタマーハラスメント防止のための体制整備が企業に求められていますが、施主などがカスタマーハラスメントといえるような行動に出たときに、従業員を守るためにも企業は適切な対応を取ることが必要となります。
元請や下請との間のトラブル
建設業を営む企業として、元請や下請の業者との取引や関わりは避けて通れないものと思われます。
このような繋がりは、自社の経営を安定させるなどのメリットを企業に与えますが、他方で、トラブルの要因となることもあります。
例えば、施主と元請との間で生じたトラブルを理由に、元請から自社に対する代金の支払いが遅延するなどの場合です。
この場合、民法や建設業法などを踏まえた適切な対応を検討する必要があります。
また、このように業者間の取引が継続的に行われている場合、他社や自社が倒産する際には互いに大きな影響を与えることになります。
したがって、取引先や自社に倒産の恐れがある場合は、仕掛かり中の工事の有無や、支払い未了の下請代金の有無などを踏まえた対応をする必要があります。
従業員との間のトラブルや労災問題
建設業者が法的紛争を抱える可能性のある問題は、顧客や取引先などの外部との関係だけではありません。
従業員との間で労使間紛争が生じる可能性も考えなければなりません。
賃金に関するトラブルや、退職や解雇に関する問題、さらにはハラスメントに関する紛争など、企業は労務管理において様々な配慮をしなければなりません。
建設業界において特有の問題としては、工事現場における労働災害があります。
企業は労働安全衛生法に基づく労働者に対する安全衛生対策をする必要があり、また、労働契約法に基づいても企業は労働者に対する安全配慮義務を負うため、これに違反して労働者に損害を生じさせた場合には損害賠償義務を負うこととなります。
労災保険では慰謝料が支払われないなど、全てが補填されるわけではないため、この補填されない部分について企業が賠償義務を負うかどうかが問題になることがあります。
また、労働安全衛生法違反に対しては企業に刑事罰が科される恐れのある他、行政処分がなされ、これらが公表される恐れもあります。
小売業や卸売業において想定される法的トラブル
顧客とのトラブル
小売業や卸売業を営む企業が遭遇する法的トラブルにはどのようなものがあるでしょうか。
まず、想定されるのが顧客との間のトラブルです。
小売業であれば顧客は一般消費者になります。
昨今、一般消費者とのトラブルで注意喚起されているのが、いわゆるカスタマーハラスメントです。
顧客からの不当な言動により従業員の就業環境が害されるカスタマーハラスメントを放置すれば、顧客との間のトラブルが解決しないだけでなく、従業員の不満が溜まり、従業員と企業との間のトラブルにも発展しかねません。
令和7年4月現在の国の方針としても、カスタマーハラスメントに関する従業員相談窓口の設置などの従業員保護に向けた体制整備を企業に義務付ける法改正を目指すとされています。
また、小売業は一般消費者に向けて広告を出すことや商品内容を表示することが多いと思われますが、その際には景品表示法に抵触していないかどうかに注意する必要が生じます。
さらに、多くの顧客を獲得するためにE Cサイトを活用する場合には、個人情報保護法に基づいて個人情報の管理にも注意しなければなりません。
卸売業であれば、販売先となる他の卸売業者や小売業者が顧客となりますが、例えば、販売先が倒産の危機に陥った場合、売掛金の回収が問題となります。
この売掛金の回収について、売掛金を買い取るファクタリングというサービスを聞いたことがあるかもしれませんが、昨今、その実態は高金利の貸付であるという偽装ファクタリングを行う業者もいるため、注意が必要です。
そのような業者の場合、買取代金が売掛金の金額よりも著しく低額であったり、高額の手数料が引かれてしまいます。
そして、売掛金を買い戻すことなどが契約に含まれており、その業者から高額の金銭の支払いを請求される事態となってしまいます。
商品の仕入れなどの場面での取引先とのトラブル
次に、商品の仕入れ元などの取引先との間でトラブルが生じることも想定されます。
例えば、仕入れた商品に不具合があったり、契約内容の解釈について取引先の認識と相違があったりすることにより、紛争に発展することがあります。
また、フランチャイズで商売をしているのであれば、本部(フランチャイザー)との間でトラブルが生じることもあります。
フランチャイズに関するトラブルとしては、商品や原材料の仕入れ先の指定に関する問題、中途解約時の違約金トラブル、契約終了後の競業避止義務の問題などが考えられます。
さらに、店舗やテナントを賃借している場合、賃料の増額や賃貸借契約の解除、解約・更新拒絶、原状回復費用などについて賃貸人との間でトラブルが生じることもあります。
従業員とのトラブル
想定される法的トラブルは会社の外だけとは限りません。
むしろ会社内部での法的トラブルの方が多いという印象があり、従業員のことで会社が弁護士に相談するということは頻繁にあります。
従業員との間で労働問題に発展した場合に適切に対応する必要があることは言うまでもありませんが、労働問題に発展することのないように法的ポイントを押さえた労務管理を普段から行うことも重要となります。
昨今ではハラスメントに配慮した労働環境の体制整備が法律上企業に義務づけられているため、この点の対策を強化することも必要でしょう。
また、小売業のような在庫商品を抱える企業特有のトラブルとして、従業員による商品などの横領の問題があります。
横領や窃盗の問題が生じた場合、懲戒解雇などの労務上の手続きだけでなく、民事と刑事に関する手続きの対応も検討する必要が生じます。
保険代理店が直面しやすい法律問題とは
顧客からの相談への対応
保険代理店を経営する皆様が直面しやすい法律問題として、まず顧客である保険契約者から法律に関する相談を受ける場面が考えられます。
典型的には、自動車保険の契約者やその家族が交通事故の被害者になった場合です。
交通事故の加害者になった場合には、保険会社が示談代行により対応することになりますが、被害者になった場合には原則として保険会社が代行することはできないため、被害に遭った顧客が自ら加害者側の保険会社とのやりとりを対応しなければなりません。
この点、昨今の自動車保険には弁護士費用特約が付帯されていることが多いため、この弁護士費用特約を用いて弁護士への相談や依頼を検討することになりますが、顧客のためにスムーズに弁護士を紹介することができれば、顧客も安心できることでしょう。
また、顧客から事業や相続、離婚などに関する相談を受ける機会もあるのではないでしょうか。
これらの問題は弁護士でなければ解決できないことが多いため、このような場合にも弁護士へ繋げることができれば、顧客は大いに助かることでしょう。
顧客とのトラブル
顧客から相談を受ける機会が多いと思われる保険代理店業界ですが、残念ながら、その顧客との間でトラブルが生じることもあると思われます。
顧客とのトラブルについて即座に弁護士対応が必要となることは多くないかもしれませんが、法律上どのような対応が妥当なのか、紛争が発展すればどのような事態が生じるのかなどについて、法律の専門家である弁護士への相談は欠かせません。
普段から相談することのできる顧問弁護士がいれば、このようなトラブルにスムーズに対応することができます。
労使関係や組織再編に関する法律問題
保険代理店に限る話ではありませんが、社員との間で労働問題が生じることは少なくありません。
労働審判や訴訟などの本格的な紛争が生じた場合に限らず、普段の労務管理に関する法律問題や、紛争に発展する兆候の見られる段階においても弁護士へ相談しておくことは重要となります。
また、保険代理店では社員が独立することや、組織体制を再編することがしばしば見られます。
そのような際に法的リスクを回避するための法的文書の作成などを検討することが必要になります。
保険会社や他の保険代理店とのトラブル
保険会社や他の保険代理店との間で法律問題が生じることも起こり得ます。
認識の食い違いやコミュニケーション不足、従前の確執など、その原因は様々ですが、そのようなトラブルが生じた場合、法律の専門家である弁護士に代理人として対応してもらうことにより、自社の負担が大きく軽減することが期待できます。
また、大きな紛争に発展する前に継続的に弁護士へ相談することにより、法律上の問題が早期に解消することもあるでしょう。
ハラスメント防止のために全ての企業に求められる対応
※2024年2月現在の法律や裁判例に基づいたコラムになります。
職場でのパワハラやセクハラ、マタハラを防止するために
パワハラ、セクハラ、マタハラは職場での3大ハラスメントと言われています。
企業の規模に関わらず、どの職場でも起きうるハラスメントです。
したがって、企業としては、この3つのハラスメントを防止することが重要となります。
まず、パワハラについては、いわゆるパワハラ防止法(労働施策総合推進法)において、①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものと規定されています。
もっとも、これらの条件は絶対的なものではなく、形式的にこれらの条件に当てはまらなくともハラスメントに当たる可能性があるため、注意が必要です。
次に、セクハラについては、男女雇用機会均等法において、職場での性的な言動に対するその労働者の対応により不利益な労働条件を受けることや(「対価型」)、当該性的言動により労働者の就業環境が害されること(「環境型」)という2種類が想定されています。
そこで、この2種類を念頭にセクハラに該当する待遇や言動が無いかどうかを注意することになります。
最後に、マタハラについては、働く女性が①妊娠・出産に伴う就業制限や産前産後、育児休業などによって業務上の支障が生じることを理由として、解雇や雇い止め、自主退職の強要、配置転換などの不利益や不利な扱いを受けたり、②妊娠・出産に伴い、精神的、身体的な嫌がらせを受けたりすることという2種類が想定されています。
パワハラ防止法などによる法規制の強化
パワハラについては、前述のパワハラ防止法が2019年に成立し、企業などの事業主に対するパワハラの防止措置義務が定められました。
パワハラ防止措置の義務については、パワハラ防止法の成立当初は中小企業については努力義務とされていましたが、2022年4月から中小企業を含む全ての事業主に対する正式な義務とされました。
したがって、現在では、企業の規模を問わず、全ての企業はパワハラを防止するための措置を取らなければならないこととなります。
また、セクハラ、マタハラについても、男女雇用機会均等法が企業などの事業主に対して、セクハラやマタハラにより労働者の就業環境が害されることの無いように、必要な体制を整備することなどを求めています。
企業に求められる体制の整備とは
前述のとおり、ハラスメントに対する法規制の強化が進められており、全ての企業にハラスメント防止のための体制整備が求められています。
それでは、体制の整備とは、具体的にはどのようなことをすれば良いのでしょうか。厚生労働省の指針も踏まえると、主に以下のような措置が雇用管理上講じられるべきとされています。
①ハラスメント防止の方針や規程の作成、社内周知
②社員啓発のための研修等
③適切に対応することのできる相談窓口の設置、社内周知
①については、ハラスメント防止に関する規程やガイドラインを作成して社内で周知する方法の他、社内報やポスターなどでもハラスメント防止を呼びかけることが考えられます。
②については、職階別に分けて研修を実施する、社内アンケート調査も併せて行うなど、いくつかの実施方法が考えられます。
③については、社内に相談窓口を設ける方法の他、外部機関へ相談担当窓口の運営を委託するという方法もあります。
当事務所では、①ハラスメント防止規程等の作成、②ハラスメント防止に関する研修、③相談窓口の運営のいずれについても、弁護士が対応することが可能です。
弁護士に協力を求めることにより、法律知識や法律上のポイントに基づいた対応をすることが可能となりますので、ぜひご検討ください。
なお、相談窓口の運営を当事務所へ委託した場合、違法行為などに関する内部通報制度にも併せて対応いたしますので、企業内で自浄作用が働くことも期待できます。
正規労働者と非正規労働者との間で異なる待遇を設ける際の注意点
※2023年8月現在の法律や裁判例に基づいたコラムになります。
「同一労働同一賃金」の基本的な考え方
正社員(無期雇用のフルタイム労働者)と非正規労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間で異なる待遇を設ける企業は多いと思われます。
しかしながら、その際、「同一労働同一賃金」の考え方に基づき、不合理な待遇差を設けてはならないとされている点に注意しなければなりません。
正社員と非正規労働者との間の不合理な待遇の相違、差別的取り扱いを解消するというのが、「同一労働同一賃金」の基本的な考え方になります。
「同一労働同一賃金」については、かつて労働契約法で定められていましたが、働き方改革関連法の改正により、パートタイム有期雇用労働法と派遣法で定められることになりました。
これにより、行政指導等の行政上の取り締まりの対象となりました。
基本給、賞与、各種手当などについて個別に判断する必要がある
働き方改革関連法の改正の前後いずれにおいても、正社員と非正規労働者との間で不合理な待遇差を設けてはならないとされています。
そして、原則として、基本給や賞与、各種手当などのそれぞれの労働条件について、一つ一つ個別に比較して判断するとされています。
また、「同一労働同一賃金」と呼ばれていますが、賃金だけでなく、福利厚生や休暇などの待遇についても不合理な差を設けてはならないとされています。
それでは、各労働条件を個別に判断するとしても、具体的にはどのように判断すればよいのでしょうか。
厚生労働省が示すガイドラインにおいては、例えば、賞与に関しては、会社の業績等への労働者の貢献度に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならないとされています。
また、例えば、役職手当に関しては、役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならないとされています。
もっとも、ガイドラインを見れば不合理な差異かどうかを簡単に判断できるというものではなく、結局のところ、裁判例の動向も踏まえた上で事例ごとに詳細に判断しなければならないということになります。
なお、定年退職後に嘱託社員などとして同じ企業に再雇用される例が多くありますが、この場合も同一労働同一賃金に配慮する必要があるため、注意しなければなりません。
これまでの最高裁裁判例でどのような判断がされているか
・各種手当
最高裁平成30年6月1日判決(ハマキョウレックス事件)においては、例えば、契約社員と正社員の皆勤手当の違いについては、契約社員と正社員の職務内容が同じであり、出勤する者を確保する必要性に差異は無いなどとして、不合理な差異であると判断されました。
他方で、住宅手当の違いについては、契約社員が就業場所の変更が予定されていないのに対し、正社員は転居を伴う配転が予定されており、住宅に要する費用が多額になり得るなどとして、不合理な差異ではないと判断されました。
ここで注意する必要があるのは、皆勤手当の違いはNGで住宅手当の違いはOKであるというような単純な判断ではないということです。
それぞれの企業における各労働者の職務内容や、それぞれの手当の内容や趣旨などを考慮した上で、あくまで個別具体的に判断しなればならないのであり、上記の最高裁判例はその判断の一例に過ぎないということを理解する必要があります。
・基本給
最高裁平成30年6月1日判決(長澤運輸事件)においては、正社員と、定年退職後の嘱託乗務員との基本給の差異について、嘱託乗務員の歩合給や正社員の能率給を合わせて比較すると、その金額差は最大でも約12%にとどまっていること、嘱託乗務員は要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けること、調整給2万円の支給もあることなどの各事情を踏まえ、不合理ではないと判断されました。
・賞与
最高裁令和2年10月13日判決(大阪医科薬科大学事件)においては、正職員とアルバイト職員との職務内容の差や、配置変更範囲の差、正社員登用状況などを踏まえ、アルバイト職員と新卒の正職員との年収差が55%程度にとどまることも考慮した上で、賞与についての正職員とアルバイト職員との違いは不合理とまではいえないと判断されました。
・今後の注目となる裁判例
これまでの最高裁裁判例を見ると、各種手当については不合理であると判断されたものがいくつか見受けられるのに対し、基本給と賞与については不合理でないと判断されたものがほとんどになります。
しかしながら、前述もしたとおり、基本給だからOK、賞与だからOKというものではなく、全ての事例において個別具体的に判断しなければなりません。
2023年8月現在の注目の裁判例として、最高裁令和5年7月20日判決(名古屋自動車学校事件)があります。
この事件では、定年退職後に再雇用された嘱託職員と正職員との待遇差が問題となりました。
各種手当についても争点となっていましたが、基本給と賞与について、名古屋高等裁判所は、正職員を定年退職したときの基本給・賞与と、嘱託職員としての基本給・賞与とを比較して、60%を下回る部分については不合理であると判断していました。
このように、高裁判決は60%を一つの基準として示していました。
ところが、最高裁判所は、基本給の性質や目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が不合理とした高裁判決の判断には誤りがあるとしました。
また、賞与についても、その性質や目的を踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が不合理とした高裁判決の判断には誤りがあるとしました。
最高裁は、上記のような事情について考慮せよという方針を示したのです。
最高裁はこのような判断をもとに、審理を高等裁判所に差し戻すこととしたため、高等裁判所において改めて審理がされることになりました。
高等裁判所が示していた60%という基準が最高裁によって破棄されたため、差し戻し後の高等裁判所でどのような判断がなされるのか、注目されるところです。